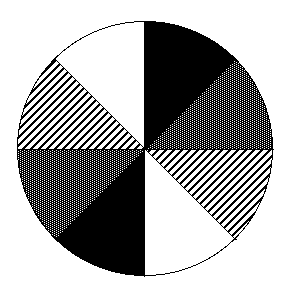1. はじめに
現代社会は目まぐるしく変化しており、今まででは考えられなかったような事件や問題が多発している。そしてそれらの根本的な解決策を見い出すことができないまま、問題に対処するための対策がさらなる問題を引き起こす、といった悪循環を引き起こしている。
この行き詰まりを打開するためには、どうしたらよいのだろうか。今までのやり方を踏襲するならば、未解決の問題を完全に解決するためには、さらなる研究、もっと多くの時間、費用、人材が必要なのだということになるであろう。
しかしながら、そのようなやり方では莫大な財源と人力が必要となる。私たちはしなければならないことに追いまくられてますます疲弊する。また、時間的にもそのような悠長なことを言っている場合ではない。さまざまな人間活動の結果引き起こされた地球環境破壊は、もはや待ったなしの段階にまで来ているのである。
つまり今求められているのは問題の本質的な解決である。今までの発想を大きく転換して、全く新しいやり方で、すべてを根本的に解決できる方法を探す必要があるのだ。
本論は、その方法を言語のさまざまな様相をもとに探ろうとするものである。
2. なぜ言語なのか?
問題の根本的な解決を探る手段は、必ずしも言語である必要はない。全く異なる分野であっても、最先端の研究をしている者同士は、どこかで通じ合うものがあるという。何学であれ、本質はみなどこかで繋がっているのである。つまり、どのような学問分野であれ、すべて物事の根本に通じるものがあるということである。
故に、言語を通して物事の本質に迫り、そこからすべての問題の解決の糸口を探ることも可能である考えられる。とりわけ言語は、人間の思考と認識そのものを規定する大変重要な要素であるから、最もその対象に相応しいと言えるだろう。
3. 研究の方向性について
今までの研究は、分析によるものが主流であった。分析のためには物事を細分化する必要があるが、それはすなわち、研究対象が果てしなく増加し、複雑化していくことを意味する。つまり、分析による研究には終わりがないということである。
また、物事を細分化すればするほど、かえって全体像は見えにくくなる。これでは永遠に答えは出ないことになり、問題の根本的な解決は望むべくもない。
問題の根本的な解決を目指すためには、全体を見なければならない。そして、複雑化ではなく、単純化の方向に向かわなければならない。そのようなアプローチこそが、物事の本質に近づくことを可能にするのである。
では、問題を単純化してなおかつ全体を見るにはどのようにしたらよいのだろうか。それを言語の様相をヒントに探っていこうとするのが、この論の趣旨である。
4言語を通して見た物事の本質
4-1 部分と全体の関係について
まず最初に、言語における部分と全体の関係について考察する。
言語学の基本的な考え方のひとつに、「言語は体系をなしている」というものがある。言語のいかなる部分も、それだけ(単独)では意味をなさない。つまりどの部分も、全体との関連性の中においてのみ、意味を持つことができるのである。いわゆる構造主義の考え方である。
たとえば、「赤い」という単語の意味は、「赤い花が咲いている。」「赤い服がよくお似合いですね。」「猿のお尻は赤い。」などのような、文脈の中での他の単語との関係[1]と、「赤い」と置き換え可能な「白い」「黒い」「青い」…などの色を表す単語群との関係[2]によって規定される。要するに、「赤い」という単語の意味は、その単語単独では規定することはできず、その言語中の他の単語との関連の中においてのみ規定することができる、ということである。
すなわち、ある言語の中のすべての単語は、その言語の他の単語との相互関係においてのみ、意味を持つことができるのである。よって、厳密に言うならば、1つの単語の意味(部分)を完璧に理解するためには、その言語の他のすべての単語の意味(全体)がわからなければならない。その言語の全体像がわからなければ、1つの単語の意味も正確にはわからないということである。
つまり、言い方を変えれば、「1つの単語の意味(部分)には、その言語のすべての単語の意味(全体)が含まれる。」と言うことができるのである。
定義上は、「部分」は「全体」の一部であり、「部分」は「全体」に含まれると考えるのが普通であるが、実はその逆も真(「全体」も「部分」に含まれる)なのである。しかしよく見ればこのような現象は、言語に限らず世の中のいたるところに現れている。木の枝を落とし、さらにその枝を落とす、というやり方で切っていけば、どんなに小さい枝でもその木全体と同じ形をしているのを見ることができるし、人間のDNAの研究は、身体のどんな極小の部分にも全体の設計図が宿っていることを示している。自然界に存在する自己相似形「フラクタル」である。要するに、「いかなる部分にも、全体の縮図が宿っている」と言えるのである。
このことから、問題解決のためにどのようなヒントが導き出せるだろうか。今までわれわれは、物事について知るために、まずそれを分析し、さらにそれについてできるだけたくさんの情報を集めることによって、一歩でもその全体像に近づこうとしてきた。けれども、無限にある情報をすべて集めることはできないし、また、分析のために部分を全体から切り離したとたん、その部分の全体との関連性は失われてしまうのだから、真実を知ることは不可能である。にもかかわらず、今までその方法は延々と行われてきた。
しかし、もしもいかなる部分にも全体の縮図が宿っているのだとしたら、どの部分でもよいから、それを極め完璧に知ればよい、ということになる。そうすれば全体がわかるはずだ。[3]
けれども、ほんの一部でも完璧に知るということは果たして可能なのか?部分を全体から切り離したとたん、全体との関連性は失われてしまうのだから、森羅万象のどの部分も、それを切り取って客観的に知ることは不可能であるはずではないか?
ところが実は、我々にとって、完全に知ることのできる「部分」がたったひとつ存在だけするのである。それはすなわち「私」(自分自身)である。「私」は「宇宙」(すべて)の一部であるのだから、私の中に「宇宙」(すべて)の縮図が宿っているはずである。つまり、すべてを知るためには自分自身を知ればいいのである。従って、あらゆる問題解決の鍵は「自分自身を知る」ことである、と言える。
「汝自身を知れ」というソクラテスの言葉は、はるか昔からよく知られている。けれども、この言葉に関して、「自分自身をもっとよく知るべきである」とか、「自分自身を知ることは大変難しいことだ」などという議論はされても、この言葉の持つ本質的で重大な意味については、ほとんど考えられて来られなかったように思う。
この言葉は、極言すれば「宇宙のすべてを知るために、自分の外の世界を考察したり、研究したりする必要はありません。あなた自身を知れば、宇宙のすべてがわかるのです。」ということなのだ。このとき、興味の関心は自分の外ではなく、内に向けられる。情報は外に向かって拡散するのではなく、自分自身の中心に向かって収斂する。それにより、すべて単純化して、本質に向かうことが可能になる。それこそが真の問題解決への道なのである。[4]
4-2 「私(自分)」の定義
とはいえ、自分自身を知ることもまた、容易なことではない。まず、「私(自分)」というものがどのように規定されるかについて考えてみよう。
普通は身体と自分を同一視するのが一般的だろう。けれども身体以外に、明らかに「自分」という心理的な領域が存在する。「自分」であると感じている意識体(心)である。この「自分」は何であろうか。
「あなたはだれですか?」と訊かれたら、たいていは名前を答えるだろうが、自分の名前がわかったからと言って、もちろんそれで宇宙のすべてがわかるはずもない。名前というのは、私に付けられたただの名称であって、私の本質ではないからである。
では、「あなたは何ですか?」と訊かれたら、どうだろうか。私ならばおそらく「人間です。」「女です。」「教員です。」「楽天家です。」などの答えが想定される。それらはすべて、何かの範疇を指し示す言葉である。つまり、自分というものを『かくかくしかじかの分類に属するもの』として捉えているということである。生物学的観点、職業、社会的な立場、性格などよって分類された範疇の総和が私である、というわけである。
しかしながらそれらもまた、「私(自分)」という存在の本質であるとは言い難い。それらは一時的に、あるいはたまたま自分が属している範疇にすぎないのであって、「私(自分)」であると自覚する意識体自体を指しているわけではないからである。
そのような分類は、「私(自分)」というものを他と区別することによって規定しようとするものである。つまり、「私(自分)」とは「他」との境界線によって規定される、というわけである。この、他人との境界線を引くことによって「(私)自分」が成り立つという考え方は、広く一般的に受け入れられていると言えるだろう。ほとんどの人が、自分と他人との間の境界線を引くことが可能だと考えているように思われる。そもそもこの社会は、「自分のもの」と「他人のもの」を区別することによって成り立っているのだから。
ところが言語学においては、「境界線を引く」ことこそ、最も困難なことなのである。言語学の範疇をどんなに厳密に定義しようとしても、必ずどちらに属するとも言えない曖昧な例が出てきてしまう。
たとえば、日本語の用言における動詞と形容詞は形式上はっきり区別できるように見える。基本的に-uで終わるものは動詞、-iで終わるものは形容詞、と言うふうに。けれども実際には、「違う」のように活用形においては形容詞のように見えるものが出現し(最近、「違かった」のように言う若者が増えている)、その境界線は曖昧になっている。
また、単語の意味においても、どこからどこまで、というふうに厳密に境界線を引くことはできない。たとえば「夕方」と言ったらだいたい何時頃かは言えるだろうが、具体的に何時から何時までかと訊かれたら、場合によって、あるいは人によって答えはさまざまであろう。
つまり言語においては、実際に存在する事象はいつも必ず連続体なので、そもそも境界線を引くことは不可能なのである。それを「私(自分)」の定義に当てはめて考えると、「自分」と「他人」の境界線は引くことはできない、ということになる。
以前の日本社会においては、自分と他人の境界線はかなりはっきりしていたように見える。また、あえて他人の領域を犯そうとする人も少なかった。けれども現代社会では、精神的にも物理的にも、今まで足を踏み入れることのなかった、他人の領域にまで踏み込んでくる人が増えて来た。そのような意味で、自分と他人の境界線はかなり揺らいできていると言える。
多くの人はそれを不安に感じている。「他人」が「自分」の領域に踏み込むこともそうだが、自分が暴走して他人に迷惑をかけることも恐れている。「自分」と「他人」の境界線がはっきりしている方が安心できるという人がほとんどで、それが存在しないということを何の抵抗もなく受け入れられる人はめったにいないだろう。それは先に述べたように、「私(自分)」は「他人」との境界線によって存在しているという認識が一般的であり、もしもその境界線をなくしたら、「私(自分)」もなくなってしまうように感じることも一因であると思われる。
けれども、境界線を引くことが不可能であるということが真実であるとすれば、そもそもないはずの境界線に固執することこそが、物事を複雑化し、問題の解決を困難にしている要因になっていると考えられるのである。とすれば、問題解決のためには、境界線をなくすことに対する恐怖感や抵抗を消し去るアプローチが必要となるわけである。[5]
4-3 認知言語学的アプローチ
そこで想起されるのが、認知言語学における意味の定義である。認知言語学は、それまでカテゴリー(範疇)によって定義されてきた言葉の意味をプロトタイプよって説明するものである。
いかなる範疇も、境界線が曖昧であるという限界を逃れることはできない。しかしながら、境界線がないからと言って、そこに全く何も存在しないというわけではない。範疇というものが想定される以上、そこには必ず何かの典型的な中心(プロトタイプ)が存在する。そしてその存在に関しては、万人の意見が一致する、というのである。
たとえば、動詞という範疇について「どこからどこまでが動詞か」を明らかにするための定義ついては、人それぞれ意見が異なり、明確な境界線を確定することはできないが、「最も典型的な動詞はどのようなものか」ということについては、意見の一致を見ることができるのだ。たとえば「‐uで終わる」、「動作を表す」、「時制がある」、「命令形がある」などの特徴を持つ「食べる」「歩く」「飛ぶ」のような単語である。これに対し、「違う」「異なる」などは‐uで終わってはいても他の要素を満たさないため、周辺的な単語であると言える。[6]
同様に、「赤い」という言葉の色の範囲は確定することができないけれども、最も典型的な「赤い」色はどれかと訊かれれば、だれもが同じ色を指し示すと言う。つまり、境界線は確定できなくてもプロトタイプは厳然と存在し、それを中心とした意味の広がりは存在するのである。[7]
このことを「私(自分)」と「他人」の問題に当てはめて考えてみると、「私(自分)」と「他人」の境界線はなくても、「私(自分)」というプロトタイプは存在する、ということになる。つまり、境界線はなくなっても、典型的な自分、最も自分らしい自分、本当の自分は決してなくならない、というわけである。
自分という存在のプロトタイプを認識し、そこにしっかり根を下ろした人は、他人との境界線が揺らいでも、動じることがなくなる。境界線の揺らぎが自分の存在根拠に何ら影響を与えないからである。むしろ、その中心から発するエネルギーと他人のエネルギーとがぶつかって生まれる、和音やハーモニーを楽しむことができるようにすらなる。
もうひとつ大切なことは、自分のプロトタイプ、典型的な自分については、万人の意見が一致するということである。つまり、それは万人に受け入れられるものである、ということだ。一般に、自分が他人に受け入れられるためには、他人に合わせなければならないと思われがちである。けれども実は、他人に合わせるのではなく、最も自分らしい自分を貫いたときに、すべての人が自分を受け入れてくれるようになるというわけだ。[8]
つまり、他人が自分の領域に踏み込むにせよ、自分が他人の領域に踏み込むにせよ、それが最もその人らしいその人、自分らしい本当の自分であるならば、問題なく受け入れられるということなのだ。このことを理解して、人生において思い切って本当の自分を出していけるようになれば、自分自身に対して自信が生まれるはずである。
本当の自分自身を受け入れることができた人はまた、他人をも受け入れることができるようになるものである。そのように、すべての人が互いを受け入れられるようになれば、必然的にこの世から争いはなくなる。
すなわち、つぎのような結論に達する。「問題解決のためにしなければならないことは、最も自分らしい本当の自分に自信を持って、それを貫くことである。」
4-4 反義語
さて、本当の自分に自信を持って、他人との境界線をなくしていけばいいことは理解したとしても、それを実践することは、容易いことではない。
他人との境界線をなくすということはすなわち、意識が今までの「自分」という枠を超え拡大することを意味する。つまり、言いかえれば「自分の殻を壊す」ということである。けれども「自分の殻」こそが、ほとんどの人が今までずっと「自分」であると信じて守ってきたものなのである。だからそれを壊すことには、当然抵抗を感じるはずである。よって今度は「自分の殻を壊す」ためのヒントについて、反義語を例にとって考えてみることにする。
反義語とは、文字通り反対の意味を持つ言葉である。「上」と「下」、「内」と「外」、「良い」と「悪い」、「開く」と「閉じる」、などがその例である。ところで、反対の意味と言えば、互いに相容れないものであるはずなのに、実は視点を変えてみれば、反義語は常に同義語になる可能性を秘めている事に気づく。
たとえば、つぎの写真のようなバスのおもちゃがある。屋根に付いているボタンを押せば、扉が横にスライドしてドアが開くのだが、そのドアのすぐ横にある窓は、横滑りした扉にふさがれて、逆に閉まってしまう。